祝!開館50周年!
板橋区立郷土資料館開館50周年
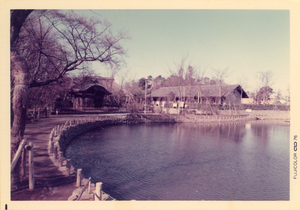
板橋区立郷土資料館は昭和47年(1972)7月23日に現在の地である赤塚溜池公園に開館し、50周年を迎えました!
この記事では、当館に残された過去の写真郡を読んでみると当時の姿が記録されていたので一部を紹介します。
始まりは板橋区史とともに
板橋区は、昭和29年(1954)に3年かけて綴った『板橋区史』の完成記念イベントとして、板橋区議会議事堂で区史編さんで活用した歴史・考古・民俗資料を一同に展示し区民へ広く公開しました。板橋区として初めて歴史・考古・民俗に関する展覧会を行いました。
この展覧会により文化財や郷土の歴史についてあらためて見直す気運が高まる機会となるはずであったが、その後、目立った活動はなく、停滞した状態となりました。
区長室の展示から産業文化会館の「郷土資料室」
昭和41年(1966)5月、当時区長を務めていた加部明三郎が「総合文化会館」の建設を意図し、区内に残る文化財、生活用品、農機具などの収集を指示しました。収集した資料たちは、区長室にケースを用意し展示されることになりました。
その後、区庁舎旧館と新館を結ぶ渡り廊下に平台ケースを並べ、区民へ一般公開させる方法も講じられました。
昭和43年(1968)、東京百年を記念し板橋区では区民が所有するお宝・家宝を展示する「東京百年記念 いたばしの秘宝展」が企画されました。この展覧会は多数の協賛を呼び、区長室の他、区長応接室、第一委員会室、助役室まで使われ、大盛況であったと伝わります。
昭和44年(1969)には、産業文化会館(栄町36番地、現在のグリーンホール)の三階の一室に「郷土資料室」の看板を掲げて開設、それまでに区民へ呼びかけて収集した民具、農機具、生活用具などを展示し、「神社と寺院宝物展」、「写真でみる板橋の史跡めぐり展」、「板橋区古美術展」などの展覧会が昭和46年(1971)10月から昭和47年(1972)2月にかけて開催されました。この郷土資料室を板橋区立郷土資料館の前身と捉えています。
郷土資料館、赤塚の地に建つ
現在、板橋区立郷土資料館や板橋区立美術館が建つ赤塚溜池公園ですが、郷土資料館や美術館が建つ前は赤塚土地改良組合が水田用として利用していましたが、不用になり売地となりました。
昭和39年(1964)3月「赤塚溜池跡地の健全なる利用に関する請願」があり、区議会で審議され、区有地となり宅地化が考えられていました。その後、高島平・赤塚・徳丸・西台地区を中心にした住民サービスの総合公園計画である「赤塚公園構想」の一環としてこの地に「教育と文化の森」の計画が立てられました。この構想のなかで、「郷土史および文化財に関する資料を一堂に収集保管、展示を目的とし、区の文化財保護行政を進める中心的な施設」として板橋区立郷土資料館が昭和47年(1972)7月23日に開館しました。現在の郷土資料館とは違い、正倉院の校倉造りを模した建物になっていました。
平成のリニューアル、令和のリニューアル
昭和47年(1972)に赤塚の地に誕生した郷土資料館ですが、施設の老朽化や増大する資料に対して手狭になりました。昭和63年(1988)10月から平成元年(1989)12月にかけて全面的に改築を行いました。平成の新郷土資料館は常設展示室、企画・特別展示室、講義室、収蔵庫など、大きく規模を拡大しました。
完成した新郷土資料館は、一般公開に先駆けて平成元年(1989)12月22日に落成式を執り行い、平成2年(1990)1月6日に一般公開を始めました。
令和2年(2020)1月8日には、平成の改築で誕生した郷土資料館の展示再整備を行い、社会科見学対応のためのメモする台の新設、タッチパネルで区内の文化財を調べられる「いたばしナビ」の設置など常設展示室を一部リニューアルし、現在に至ります。
その他、細かいことはまた別の機会に掲載したいと思います。
昔と今をくらべてみよう!
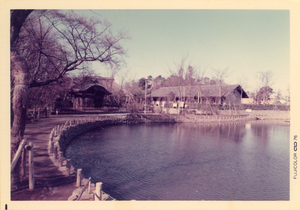











より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
板橋区立郷土資料館
〒175-0092 東京都板橋区赤塚5-35-25
電話:03-5998-0081 ファクス:03-5998-0083
教育委員会事務局 生涯学習課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。