上板橋第四小学校(令和7年6月25日訪問)
教育長訪問記
6月25日(水曜日)上板橋第四小学校を訪問しました。教育長ふらっと訪問になります。当日は本校の「いたばし学級活動の日」でした。これは板橋区独自で設定しているもので、全学級が学級活動(学級会などの話合い活動)を保護者や地域の皆様に公開するものです。令和6年度までは区内の全校で同じ日(1月中)に実施していましたが、令和7年度からは各学校で日にちを決めて実施することにしました。
下の写真のように、学級会は児童の机を移動させて、できるだけ相互に顔が見える配置にして話合いを行います。役割は様々ですが、小学校では司会・副司会・黒板書記・ノート書記の4つを役割分担していることが多いです(黒板書記を2人としている学級もあります)。最近では書記のノートを紙ではなく、一人一台端末に入力し、それを電子黒板に映している学級もあります。中学校では司会役を学級委員などに固定している学級も多いのですが、小学校では輪番制にして多くの児童に経験させている場合が多いです。

全学級を見て回りましたが、どの学級でも議題は「上四フェスタの出し物の工夫について」でした。学級ごとの出し物がどのように工夫すればより良くなるか、というものです。正解はありません。子どもたち自身で答えを、自分たちの正解を導き出す話合い活動です。教科の学習では手が挙がらない子でも、堂々と発言することができます。文部科学省の全国学力・学習状況調査では、話合い活動に熱心に取り組んでいる学級は教科学習の正答率が高いという相関が出ているのです。
下の写真の学級では、各自の意見を一人一台端末に入力し、それを電子黒板に映して、多様な意見を参考にしながら、意見を出し合い、集約する方法を取っていました。端末を活用した新しい方法と言えます。

意見を出し合った後は、多数決で決めるのではなく、合意形成を図っていきます。意見を比べ合って、どのような意見を採用すれば議題の提案理由に沿った解決になるのかを話し合っていきます。これにより話合いのスキルが身に付きます。自分の考えを押し通そうとしているだけでは集団決定に至らないからです。聞く力も必要となります。多様な他者と合意形成をしながら物事を進めていくという、将来役に立つスキルを育む機会になっています。
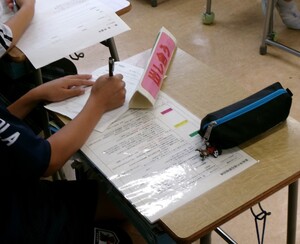
山藤校長のお話では、本校は以前から学級活動の実践に熱心に取り組んできているそうです。確かに本校では全校で統一感のある方法で話合い活動を実施していることもあって、確実に話合いのスキルが上達しています。その証拠に経験を積んだ6年生の話合いは多くの児童の意見が集約され合意に至っていました。そのプロセスも黒板などでしっかり可視化されています。5年間と約3か月の積み重ねがあるからこそと言えます。
先生によって(学級によって)話合いの方法が違っていると、子どもたちは担任の先生が変わるごとに、その方法に適応しなければなりません。しかし、学校全体で話合いの方法を統一していると、子どもたちは同じやり方で6年間、話合い活動をすることができるのです。今後は、できれば学びのエリアの小学校、中学校で話合いの方法を統一すると、さらに効果が上がるのではないかと考えています。
(記・長沼豊教育長)
関連リンク
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育総務課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2603 ファクス:03-3579-4214
教育委員会事務局 教育総務課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。

