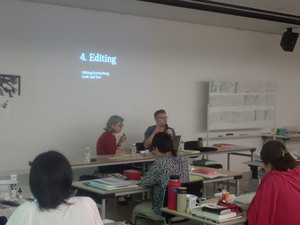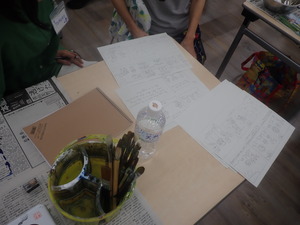2025年7月4日 夏のアトリエ・4日目
クリスさんによる夏のアトリエもあと2日。今日のテーマは「Editing」、編集です。
絵本製作の際、編集に時間をしっかりとかけるというクリスさん。その中でも、どの「人称」がその作品に一番あっているのかを考えるそうです。1st(一人称:me 私)、2nd(二人称:you あなた)、3rd(三人称:彼/彼女 he/she)の3つの人称のうち、どれを選ぶかによって作品は変わっていきます。一番よく使われるのは3人称だそうです。
こうした人称をうまく使うと、たとえば読者が知っていることも主人公は知らない、という状況が生み出されたりします。そうした視点の違いによって、おもしろみが出てくると言います。
次に「limitation(制限)」についてもお話くださいました。
例えば、英語話者には韻(rhyme)を踏んでしか文章を書けない、という人がいるそうです。これをどうしてかと考えたとき、なにかひとつ制限やルールがあった方が、テキストを書きやすいということがあるのかも、ということでした。クリスさん自身も、ルールを設けて書いているとのことでした。例えば『どうする ジョージ!』では、何かが起きそうな前兆(before)があり、ページをめくるとアクシデント(after)が起こります。そして、アクシデントが起きるときには必ず「Oh, No Giorgi!」というテキストが添えられており、そのテンポ感がおかしみをより演出しているようにも感じられます。このように、お話全体のリズムを考えることで、作品にとって効果的なパターンを見つけるとのことでした。
また、どういうリズムやテキストにするのが一番効果的かを考えるとき、クリスさんがよく使う本があると紹介してくれました。
レーモン・クノーによって書かれた「Exercises in Style」(元はフランス語より刊行。日本語版は『文体練習』として、朝日出版社より刊行)という本で、元となるひとつのテキストをもとに、同じ内容を物語、会話、手紙、詩から口語体や文語体、パロディーなどの99の文体で書いています。つい自分のお話はこう書かないと! と、つい思いこんでしまうなかでこれを読むと、こんなにたくさんのスタイルで書けるということがわかると、クリスさんはお話してくれます。
クリスさんは自身の編集者とのやり取りについてもお話くださいました。元ピエロだったという異例の経歴を持つ編集者で、クリスのテキストを演じながら読んだりするそうです。子どもの本には、大人が読んで聞かせるものという側面もありますが、この編集者と会うまで、クリスさんはそのことを考えたこともなかったと言います。このことから、どう読むことができるのかも考えるようになったとのことでした。
講義のあとには、エクササイズを行いました。まずA4の紙を2枚用意します。1枚は6つの枠に分けて、今考えている物語のシークエンス(場面)を6つ描きます。ここは物語の要となる部分を選び、結末は描きません。もう1枚の紙には、文章で物語の要約と、どういう結末になるかを書きます。これを25分間で行ったあと、3人グループになって他の2人の制作したものを読み、わかりづらいところや直した方がいいところ、オチの提案などのコメントを書きます。これは8分ずつで、編集されたものが制作者のもとに戻ります。
その編集を受け、さらに20分をかけて手直しをしていきます。もちろん、書かれたコメントをそのまま反映する必要はありません。クリスさんは、よりよい形に変えていくことを考えてください、と受講生に伝えます。
手直ししたあとは2人1組になって、お互いに自分の作品のプレゼンテーションを行います。このプレゼンは相手に伝えることに慣れるものであると同時に、自分に対してのものでもあると言います。ストーリーやテキストを声に出してみることで、頭のなかで考えていたときとは違った観点で作品をみることができるようになるとのことでした。また、話したときの反応をみて、さらに編集を加えていくこともできるようになります。
受講生は短い時間のなかで、制作・編集・プレゼン・・・を行うことになりました。絵本を制作するときは、どうしてもひとりで考えていくことが多く、悩んでしまったり、詰まってしまうことも多いと思います。そうした中で、違う人の目線を入れ、編集していくことの重要さをこのエクササイズでは学ぶことができたのではないでしょうか。自分で声を出してテキストを読んだり、説明することも、普段の制作にも役立てそうです。それぞれに気づきがあったようで、午後の制作に生かしている人も見られました。
明日はいよいよ最終日です!