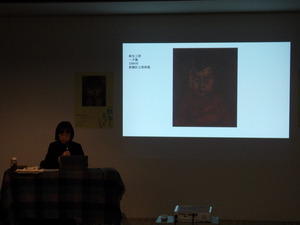2025年11月15日 戦争と子どもたち展 スライドトーク
11月8日より、企画展「戦後80年 戦争と子どもたち」がはじまりました!
本展は、日本の美術家たちが戦中・戦後を生きる子どもたちをどのように表現していたのか、また当時の子どもたちはどのような美術に触れていたのかをご紹介するものです。油彩画、日本画、版画、彫刻のほか、教科書や絵本、紙芝居といった資料も展示されています。
開幕から1週間経った本日は、担当学芸員によるスライドトークを実施しました。
はじめに、本展の企画のきっかけについてお話しました。板橋区立美術館では、池袋モンパルナスの作家による作品を収集しています。本展出展作でもある、麻生三郎による≪一子像≫(1944年、板橋区立美術館)では、麻生自身の子どもである幼児がまっすぐに前を向いた姿で描かれています。作家がこの絵を描いた当時について振り返った文章には、このころ子どものことを描かずにはいられなかった、ということが記されているそうです。この麻生の描いた子どもの絵をきっかけに、戦時下において、作家たちがどのように子どもたちを描いたのか、どのようなまなざしを子どもたちに向けていたのかを紹介する本展の企画に至りました。
本展では、赤ちゃんから今の高校生くらいまでの少年少女たちを「子ども」とし、5つの章に分けて紹介をしています。各章から数枚ずつ絵をご紹介し、展覧会の見どころをお伝えしました。
例えば、1章「童心の表象」に展示されている、青柳喜兵衛≪天翔ける神々≫(1937年、北九州市立美術館蔵)には、博多のトラ張子にまたがる子どもが描かれています。福岡出身で、東京と福岡の間を行き来した青柳は、かつて池袋モンパルナスに暮らしたこともある作家です。鮮やかな色合いであり、子どもは無邪気な様子ですが、実はモデルの少年は2年前に亡くなった青柳の息子であったといいます。
このような子どもらしい姿で描かれていたものも、段々と違った様子で描かれていくようになります。
第2章「不安の表象」で紹介している、松村綾子による≪少女・金魚鉢≫(1937年、星野画廊)や、吉原治郎による≪防空演習≫(1944-45年頃、大阪中之島美術館)など、うつむいた姿で描かれた子どもたちが登場するようになります。
また、第3章「理念の表象」では、乳飲み子を残し出征する看護師の姿や、食糧増産計画のために育てたであろう芋を掘り起こしている少女の姿などを紹介しました。そうした姿からは、戦争の理念に従っていた子どもたちの姿を見て取ることができます。
一方で、麻生三郎のように、自身の子ども姿を戦争とは異なる文脈で描いた作家もいました。第4章「明日の表象」では、本展のメインビジュアルにも使われている、松本竣介の≪りんご≫(1944年、個人蔵(板橋区立美術館寄託))をご紹介しました。本作は指をつかって描いているところもあり、松本の指の跡なども見ることができるそうです。また、同じく松本の≪せみ≫は、自身の次男が描いた絵をもとに描いたものだといいます。
最後の第5章「再建の表象」では、戦後の子どもたちの姿を紹介しています。麻生による≪子供≫(1948年、弥栄画廊)は、≪一子像≫の一子が成長した姿を描いたものです。以前描かれたものと比べると、やわらかな空気をまとっており、どこか遠くを見つめている姿などからは希望も感じられるといいます。
また、最後に中島菊夫による「慰問新聞」(1944-45年、山﨑記念中野区歴史民俗資料館蔵)を紹介しました。中野区の小学校で教えていた漫画家であった中島は、福島へと疎開した子どもたちに、手書きの新聞をつくって送っていたものだといいます。この「慰問新聞」は、本展の展覧会カタログにも再録されているので、気になる方はぜひカタログもご覧ください。
今回のスライドトークでは、30分ほどで展覧会の概要についてお話しました。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!
次のスライドトークの開催は、12月6日(土曜日)です。
「戦後80年 戦争と子どもたち」は、1月12日(月曜日・祝日)までの開催です。
多くのゲストをお呼びしてのイベントも数多く予定しています。
みなさまのご来館をお待ちしています!