2024年5月18日 講演会「江戸の洋風画と司馬江漢」
5月18日(土曜日)、成澤勝嗣先生(早稲田大学文学学術院教授)による「江戸の洋風画と司馬江漢」と題した講演会を開催いたしました。
「洋風画という風」展では、司馬江漢による作品を数多く展示しています。もっとも有名な江戸の洋風画家といえば江漢ですが、どうやら一筋ならではいかない人物だったようです。
講演会では、江漢の作品や記録についてご紹介するとともに、人となりに迫っていきました。

江漢ははじめ鈴木春信風の浮世絵を手掛け、宋紫石に学び中国式の写実的な花鳥画を学び、そして洋風画の道へ進んでいきます。
日本ではじめて腐食銅版画(エッチング)をつくった人、ということで有名です。
ということで、彼の銅版画には「日本創製司馬江漢」としっかり書き込まれています。自負心とともに、自己顕示欲も感じられます。
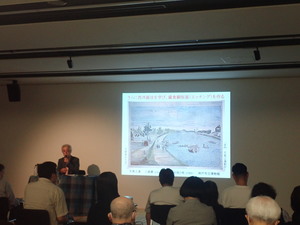
司馬江漢はイッカク(一角)という海の生きものについて関心を寄せ、その図を描いています。イッカクはその角が解毒剤として珍重され、輸入されていました。江漢が描いた図はヨンストンによる蘭書をもとに描いたもので、画中にはイッカクについての詳しい説明も書き込まれていますが、この文章は実は、同時代に活躍した蘭学者である大槻玄沢によるものだったのです。ハンコの位置からは、江漢が賛の内容を書いたとも受け取れるという、意図したような巧妙さが垣間見られます。
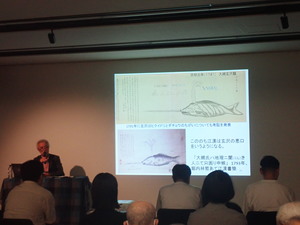
おそらくこのようなことからも、蘭学者の間では評判がすこぶる良くなかったようですが、江漢が描く作品には市井の人々へ向けたやさしい眼差しも感じられます。
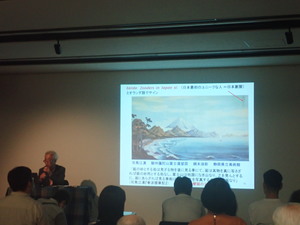
ほかにも、年齢詐称(還暦後から年齢を加算する)、まだ存命にもかかわらず死亡宣言をするなど、江漢はから破りな一面がありました。
時代が早すぎたというか、現代に生きていたらどのような作品や活動を私たちに見せてくれたのだろうかと想像したくなります。
成澤先生、刺激的な江漢話をありがとうございました。
